Black Grief
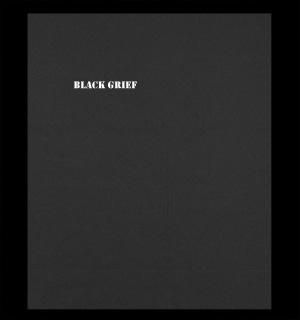 2009年の初夏から取り組み始めた構想である「Black Grief」は、百数十ページに渡るメモと数十枚のスケッチを積み重ねて深い秋を迎えてようやくある種の明快さに辿り着いた。
2009年の初夏から取り組み始めた構想である「Black Grief」は、百数十ページに渡るメモと数十枚のスケッチを積み重ねて深い秋を迎えてようやくある種の明快さに辿り着いた。
簡単にいってしまえば、喜怒哀楽のごった煮から、「哀」を抽出したパッケージを考えるというもので、これは、例えば同時期、小説家の平野が構想したディヴィジュアル(分人)というものに併置できるかもしれないが、性格は全く異なる。ディヴィジュアルがアバターのような対応分離の身体ツールとすれば、このパッケージは、身体から絞り出すエキスのひとつであり、互いに干渉することを停止した澱みであり、他と対応できない孤立の氷のようなもので、固有の色彩を持つ。
もともと現実を曖昧に出鱈目に消耗するまま、成り行きに任せるような生を送ってきた反省というのも可笑しいが、個人的な経緯の総体を振り返って、喜怒哀楽にまみれた人生でしたと一言で済ますわけにはいかないと、そもそも考えた。
いかなるものにも喩えようのない哀しみ、嘆きということは、どちらかと云えば「苦」に属するかもしれないが、自身の実直且つ時空の弁えで、まずはこれだろうと4種類からひとつを選んでいた。普段から何物かに対する憤怒に纏われたむつかしい表情をしている人間も、嬉々とした躁状態が日中降りそそぐ口元の緩んだ人間も、彼らの人生全てがそのようであるはずがない。ゆっくりとした感情の変容と流れのまま、どの淵に佇む傾向が強いか弱いかの些末な傾向なのだが、表情の表象としてアイコン化されると、傾向イコール人格とされる。彼らに共通する「哀」など無いと考えたほうがよろしい。共有の哀しみは持たないが、固有の特異な「哀」は、語られないまま抱かれてある。そのまま墓まで抱きしめていくのだろうか。大きく声をあげて笑い合った後、ふいに空しさに包まれる時もある。いたって温和な人間が、実はという話もある。では、様々なのだからさまざまであるとすれば、傾向の羅列の中に溺れるだけとなる。浮き上がって、何か精製された大気を吸ってみたいという願望があったのかもしれない。「哀」を全身に染めてみるということではなく、摘出して机の上に置く。
残された時間を「哀」だけに注ぐつもりは毛頭無いが、戦争や抑圧など特異な状況などなかったとされる時代を過ごした人間に湧いたささやかな感情の形態として示すことは、観念で相対的に意味付けることを切断する力を持つとした。自身の「哀」を考える内に、こんなことだったかと新しく気づく事もあって、曖昧だった感覚が確かなものに変わる。
繰り返し選ばれ残された表象が、ひたすら黒々とするしかなかったことから「黒い嘆き」とした。ここには、だから、歓びも怒りも愉悦も笑いも無い。ただひたすら「嘆き」として選ばれたものが、その言葉のままに置かれる。